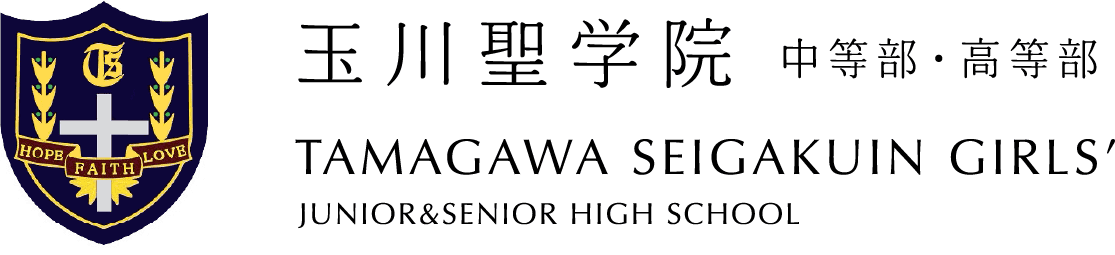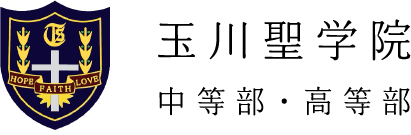今年のゴールデンウィークは比較的天候に恵まれ、薫風薫る5月の爽やかな日々を過ごすことができた。普段は忙しさの中で見過ごしてしまう周囲の自然の姿を楽しむことができた。立ち止まり五感を働かせることで、目に映る多彩な色合い、聞こえてくる数々の音色、香りや手触り、季節を感じる味覚などが、意識の中に浮かび上がってくるのを感じることができた。
最近刊行された岩宮恵子さんの著書『思春期センサー』(岩波書店2025年)を興味深く読んだ。岩宮さんの著書は以前に『フツーの子の思春期』(岩波書店2009年)を、保護者の読書会で取り上げて、大変共感を持って皆で読んだことがあった。大学教授でユング派の心理学者、カウンセラーとして小中高の教育現場と長年関わってこられた著者が、臨床の現場で接してきた子ども達の中に感じた時代や社会に映し出されている姿を、自分の言葉で語っていた。この度の新刊も、いわばご自分の臨床経験の集大成とも思われるような充実した内容で、教育現場のみならず思想や哲学を考える人たちに多くのヒントを与える内容であるように思われた。
著者は、不安定で傷つきやすく、内的エネルギーをうまく用いることができない思春期特有の心の特性を示す思春期の感受性の感知装置を「思春期センサー」と名づけ、センサーが働くことで、自己治癒力を発揮して変容していく子ども達の心を見つめてきた。そして周囲の大人がそのセンサーを認識し、苦しむ彼らへの理解を深められるかが問われていることを書き記していた。
「マスコミでの報道やネットニュースのタイムラインは、微妙なニュアンスを排除し、
単純で大きなざっくりとした目盛りで判断して、その枠組で伝えることに特化して
いるように思う。そのほうが「伝わりやすい」という判断があるのだろう。
そういうマスコミの目盛りはたとえて言うと、ひと目盛りが10cm くらいの幅に
なっていて、その目盛りと目盛りの間はないことになっている・・・・彼らの心の
目盛りは、1mm 単位だ。つまり、マスコミ的なものの100倍、細かい差異を感じ
取る力がある。この差異を感じ取る能力が思春期センサーの感度の精度を表すもの
であり、感受性の強さを示すものである。・・・一般的に思春期の心はその感性の
目盛りが人生の中で一番、細かく刻まれている時期だ。」
SNS環境の日常化や人間関係の構築の難しさ、同調圧力の強さや競争原理の刷り込みがもたらす社会的影響が強まる中、子ども達の育ちの環境はますます厳しくなっている。著者は自らの心を開きつつ子ども達と向き合い、彼らの中に起きている現象や心の変化を的確に言語化する。この思春期の特性が年齢を超えて拡大し社会全体に広がっていることも指摘する。
子ども達の現状を読むことで分かったようなつもりになって、外から批判的に眺めていることの危うさを思う。自らの内発的な力で変容を遂げていく子ども達に寄り添うことの難しさと共に、分からなくてもわかろうとしてくれる存在があることは、彼らの傍にそういう大人がいることが大事だと思う。社会全体に人間理解の目盛りの精度を上げていくことが望まれているのではないか。
温かい日差しの中、新緑の木立の中を通り抜けてくる5月の風に心地良さを感じつつ、いつまでも自分自身の心の感度が錆びつかないようにしていきたいと思わされている