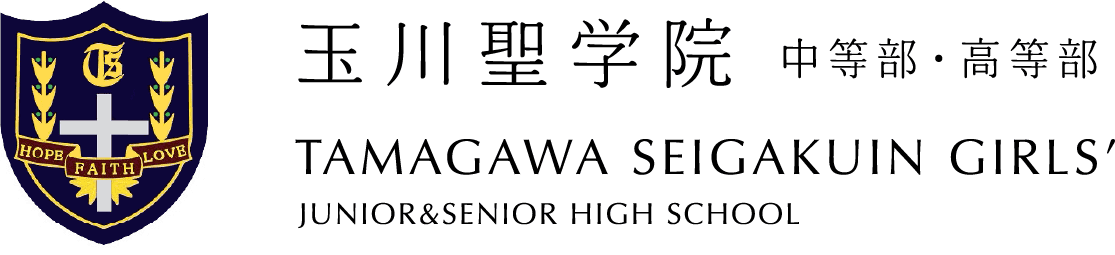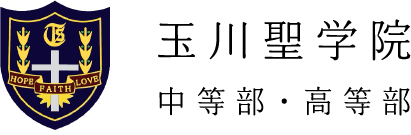2月は入試の季節。希望する学校へ合格するために、受験生は多くの犠牲を払ってそれに備え、蓄えてきた知識を最大限に動員して入試問題に向かっていく。入試の緊張感を多くの人は原体験として持っているだろうし、一つの壁を乗り越えることで人生の次のステージに向かっていったことを記憶していることだろう。今年も中学、高校、大学入試が各地で繰り広げられている。本校においても中高それぞれの入学試験を無事に終えることができた。
今月の読書会は、戸谷洋志著「親ガチャの哲学」(新潮新書)を読んだ。くじの当たり外れのように、どういう親の元に生まれるかで人生のかなりの部分が決まってしまうという考え方だ。そう思っている若い人たちがかなりいることについて色々考えさせられる本だった。生まれた環境の差異は個人の努力では乗り越えられないほど社会的格差が大きくなっていることの表れなのだろうか。苦境にある人が努力不足の結果と言われるのが残酷なので、「親のせい」と言えば楽になるからなのか。虐待やネグレクトの増加に見られるような親子関係の基本的構造が変化してしまった故なのか。出生により人生の幸・不幸が決まるという考え方が広がっている。それは「生まれなかった方が良かった」という反出生主義思想が広がっていることにも通じる。
人間の心は複雑で、折々に色々な思いや願いが沸き起こってくる。その複雑さや不可解さこそが、心の成長にとって大事な要素となる。喜怒哀楽を伴う様々な感情を体験しながら、自分を知り、他者を理解し、世界を認知していく。しかし今日の課題は問題を単純化して、すぐに正解を求め結論づけようとすることではないか。答えの出ない問題を持ち堪えて、自らで考え続けようとしないことにあるように思う。簡単に白黒の決着をつけてしまう。だから自分の人生までモノ化して考えてしまう。分断された社会に漂う孤独感はそれを助長している。希望が失われニヒリズムが人々を支配し、思考停止状態に追い込まれていく。
著者は「親ガチャ的厭世観を乗り越えるためには、社会による連帯が必要だ」を述べているが、改めて考えるのは「人は人との関係性の中で人間になっていく」という人間本来のあり方をどうしたら取り戻せるかということだ。諦めと絶望に覆われている苦境にある人が、自分の人生を自分のものとして引き受けていくには、人との関係の中で出会いを経験し、居場所が確保され、存在自体が肯定されていく経験が必要なのだろう。自分の声を聞いてくれる誰かが存在すれば、孤独から生ずる絶望や自暴自棄を回避できる。そのためには、「親ガチャ」というしかない人が持つ心の痛みに対する想像力を持ちつつ、孤立しないような緩やかな連帯を作り出していくしかないような気がする。そして全ての人が若い時に原体験として人と共に歩む幸いを味わえる社会(学校生活)を保障していくことが本当に必要ではないか、真の教育の課題はそこにあるのではないかと思わされた。