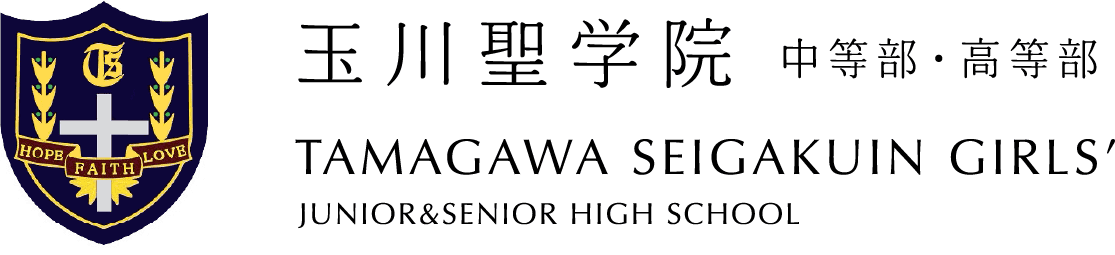日に日に鮮やかな緑に覆われていく季節となった。コロナ禍でステイホームを余儀なくされてから4年の年月が経過した。用心深く公共施設や電車内などではマスク着用は続いているが、互いを知り合う集団の中では、以前のような生活スタイルに戻ってきたように思う。社会的な対応も変わって一年を経過し、学校でも普通に行事や活動が行われるようになった。改めてこの間に得たものと失われたものについて考えた。
人は人との関係の中で成長していく。それを支えるのが教育であるとしたら、ソーシャルディスタンス、人との距離を取ることを要請されたこの間の関わり方は、かなり異常なものであったのだろう。すぐにそれに慣れてしまい、人との近すぎる関係を懸念している自分がいることを発見し驚くことがあった。黙食という習慣は子どもたちに何を与えてきたのだろう。体験的な学びが十分に提供できなかった学校教育で失われたものは回復することができただろうか。各学校で不登校や転学者が急増した背後に、十分に発達の課題と向き合えなかった「時の問題」があったのではないか。空白を埋めるだけのフォローを教育は提供できているだろうかと考える。
同時に、コロナ禍で改めて発見したことも多かった。自分にとっては「生物の成長の時間感覚」への気づきが大きかったと思う。旅行などできなかった反面、散歩などで自然に触れる機会が多く、その存在と営みについて深く考えさせられた。新鮮な感覚で観ることや聴くことなど、五感を通して自然の姿に触れ、そこに流れる時間について、立ち止まって考える機会も多かった。
そんな思いの中、五月の読書会はドイツの森林管理官ペーター・ウォールレーベンさんの書いた『樹木たちの知られざる生活』(早川ノンフィクション文庫)を取り上げ学ぶことになった。冒頭で著者は「私は樹木たちの秘密についてほとんど知らなかった」と書いている。仕事を続けるうちに知らされた自然林の奇跡や不思議を感動を持って記しているのだが、全くの門外漢である自分にとって、目覚めさせられる書物だった。また、この数年の間考え続けている「成長の時間感覚」を再考させる内容だった。
「若木は生長したがる。一年で50センチほど大きくなれる力を持っているが、母親がそれを許さない。・・・子供ブナの頭上に大きな枝を広げ、葉に届く日光を遮り森の屋根を作る。子どもの葉に届く日光はたった3%。死なずに済むだけの光合成しか出来ない。これが教育だ。ゆっくり生長するのは、長生きをするために必要な条件だという。植林された木は80〜120年で伐採され加工されるが、野生の樹木は100歳前後でも鉛筆ほどの太さで、背の高さも人間程度しかない。ゆっくりと生長するおかげで内部の細胞が細かく、空気をほとんど含まない。柔軟性が高く、嵐が来ても折れにくい。抵抗力も強いので、若い木が菌類に感染することはほとんどない。少しぐらい傷ついても皮がすぐ塞いでしまうので腐らない。優れた教育こそが長生きの秘訣なのだ。」(要約)
人が自然の中に佇む時、忘れている生物の時間感覚を思いやることができる。詩人長田弘さんの詩集『人はかつて樹だった』(みすず書房)の中に「森のなかの出来事」という詩がある。
「森の大きな樹の後ろには、過ぎた年月が隠れている。
日の光と雨の滴でできた 一日が永遠のように隠れている。
森を抜けてきた風が、 大きな樹の老いた幹のまわりを一廻りして、また駆けだしていった。
どんな惨劇だろうと、森のなかでは、すべては さりげない出来事なのだ。
森の大きな樹の後ろには、すごくきれいな沈黙が隠れている。
みどりいろの微笑みが隠れている。音のない音楽が隠れている。
言葉のない物語が隠れている。・・・・・・・・・・」
結果と成果だけが求められる社会に飲み込まれずに、真の成長を促す視点を忘れないようにしたい。そのためにも、時々、森の中で静まる経験を重ねていきたい。