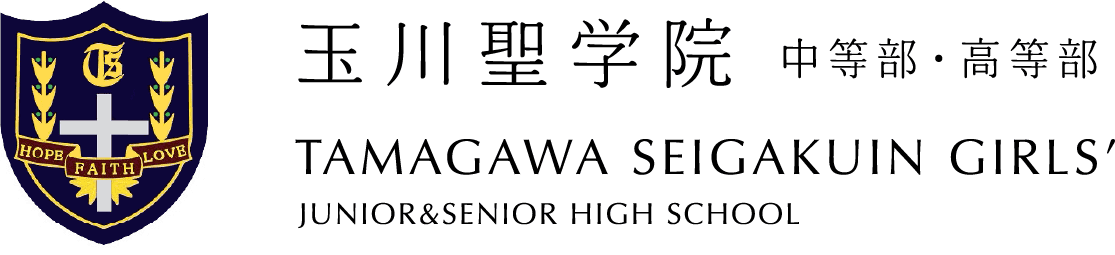学院祭も一部生徒がコロナ禍のために登校できないことも起こったが、無事に終了できて今月は校外宿泊行事が計画されている。まだまだ以前の日常が戻ってきたとは言えないが、安全への配慮と工夫の中で、学校生活が営まれていることを嬉しく思っている。生徒たちの学校生活の表情にも落ち着きが見られるようになってきた。
10月の保護者読書会では、レーチェル・カーソン著「センス・オブ・ワンダー」を一緒に読んだ。8年前に一度取り上げたが、文庫版(新潮文庫)で、同時に四人の識者の文章が記載されていることもあり、もう一度読み直した。生態系が破壊されていく現実に警鐘を鳴らす「沈黙の春」を出版したことで、社会に大きな衝撃を与えると同時に凄まじい攻撃を受けた著者が、病身の中でいわば遺言的なメッセージとして書き残した本著は、何度読んでも味わい深い珠玉の言葉に満ちている。享年57歳は若すぎる死だ。
海洋生物学者であると同時に、大自然の神秘に満ちた輝きを言葉で表現する詩人でもあったレーチェル・カーソンならではの散文詩のような美しい文章は、生き生きと読む者の心に伝わってくる。姪の子どもにあたる幼いロジャーと共に体験する、自然が彩なす神秘的な世界の探検は、自然をありのままに見ようとする科学者の眼と、その神秘を大きな体系の中に位置付けようとする哲学者の心を併せ持つ洞察力を読む者に感じさせる。
「もし、私が全ての子どもの成長を見守る善良な妖精に話しかける力を持っているとしたら、世界の子どもに生涯消えることのないセンス・オブ・ワンダー(神秘さや不思議さに目を見張る感性)を授けてほしいと頼むでしょう。」
感じる心は体験により育てられていく。その感覚の土台の上に、自発的な探究心が生まれ、知識が積み上げられていく。知性と感性が折り重なるように芽生え育ち、自らの意志を働かせる事で内的世界は広がっていく。心が育つとはそういう事なのだろう。子どもたちに与えたいのは、知識ではなく、探究心を呼び覚ますような体験を一緒に味わう事なのだろう。教育とは本来そのような営みなのだ。コロナ禍を経験した後に再読した本著は、より味わい深いものだった。以前には深く感じられなかった言葉が輝いて見えてきた。聞こえなかった著者の声が聞こえるような気がした。次世代を生きる者に伝えようとしたメッセージを聞き取ることができた。
再読した時に新たな発見がある書物は、読み手にとって大事な本となる。読み手の関心の領域が変化したからか、未熟さの故に理解できなかった著者の主張が少しわかってきたからか、人生経験がそれを可能にしてきたのか理由はわからないが、新たな発見体験はとりわけ嬉しい気持ちにさせられる。何度も何度も繰り返し読める本を持っているのは幸いなことだ。
若い時に出会った一冊の本が、生涯のマイブックとなるのであれば幸いだ。一つの絵画や音楽、詩歌や特定の原風景を「私のもの」として、折に触れて向き合うことができたら、より豊かな人生を送れるのだろう。あまりに情報が拡大した時代だからこそ、一つのものに収斂していくベクトルを大事にすることを、次の世代に伝えていきたい。そんなことを感じさせる再読の機会だった。