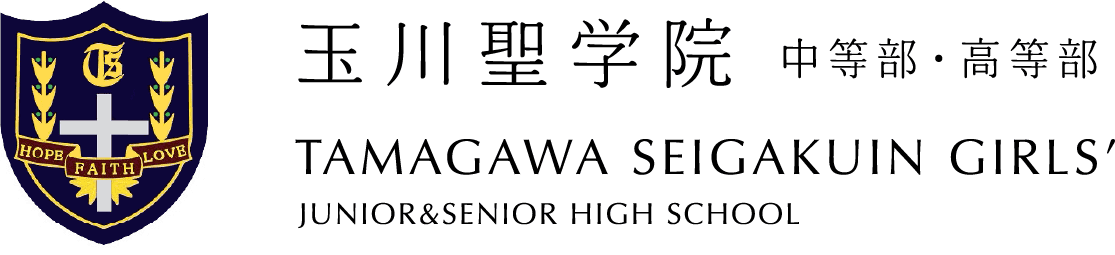年明け早々、能登半島の大地震そして羽田での航空機接触事故と驚く出来事が続いた。寒さの中で愛する人や財産を失い、生活の基盤を壊された人たちのことを思うと言葉を失う。旧知の人たちをはじめ北陸に住む方々を襲う心の痛みに思いを巡らすと、祈るしかない我が身の無力さを思う。同時に元旦以来、目にする報道の数々そして発信されるSNSの多くの情報の中に、この社会が大きく分断されていることを感じる。とりわけ互いの発言や行動を否定し合う、攻撃的な言説が飛び交っていることに絶望感を強く感じている。多くの人たちの言動には、自分の見える世界(近景)と誰もが認める真理(遠景)に間に存在するはずの、相互に作り出す公の場としての社会(中景)が置かれていないように感じる。全く対話が成立していない。
今から10数年前に東日本大震災が起きた時、その直後に福島の原子力発電所の事故が報じられ時、社会は未曾有の恐怖に包まれた。震災の晩に何百人かの生徒を学校に留め置いて、教職員たちと共に一晩を過ごした日のことを忘れられないが、あの時は社会全体には危機意識を共有しようとする空気が満ちていたように思う。「危機の時には常態が現れる」と言われるが、今回の政治を含めた社会全体の対応に、現在の日本社会の実質が現れているように思えてならない。
何故、私たちの社会はこれほどまでに分断されてしまったのだろう。幻想に過ぎなかったかもしれないが、昭和の時代に青年時代を過ごした世代には、未来に対する希望や共通のコンセンサスがあったように思う。また努力次第で小さな夢を実現できる場を探すことも出来たような気がした。だがその後の社会では未来は「バラ色からイバラの道」に変わり、「努力次第で状況を変えられる」と説くことは、自己責任論を促す競争主義の論理である「頑張らなければならない」という呪詛の言葉に変質してしまったようだ。バブル崩壊後の30年、新自由主義に基づく物の考え方は社会的格差の拡大を肯定し、社会のセーフティネットを外させ、人と人とのつながりを壊していったのではないか。
かつてレベッカ・ソルニットは「震災ユートピア」(亜紀書房2010)の中で、大きな災害の中で社会全体がどのような行動をとったかを実証的に調査して、「人々が助け合い、協力する、即席の地域社会が生まれる。団結と利他主義が大事な場面で現れる。震災が起きた時、人々はどうすべきかを知っている。」と記していた。危機の中で苦しみを分かち合う人々の善意が呼び覚まされて、本来人間が持っている相互扶助の精神が目覚めることを伝えていた。
地震発生から2週間余りの日々の中で今後を決めつけることはできないが、人々の意識は遠いところで起きた極めて限定的な場所の災害のように感じているのだろうか、社会に危機意識は共有されていない。この30年間に培われてきた「他人に迷惑をかけない」そして「他人に干渉しない処世術」が広がる中、他者への無関心と孤立が人とのつながりの構築を妨げている。
つながりの再建はどうしたら可能になるのだろう。社会の分断はあらゆる場所で広がっている。そうだとしたら、やはり身近なところから、自分自身のつながりを作り直していくことが必要なのだろう。自分と少し立場や境遇の異なる人、少し疎遠になりつつある旧知の友、新しい刺激を与えてくれる異世代や異文化の中にある人に、自分から積極的に接近していくことが求められているように思うのだ。