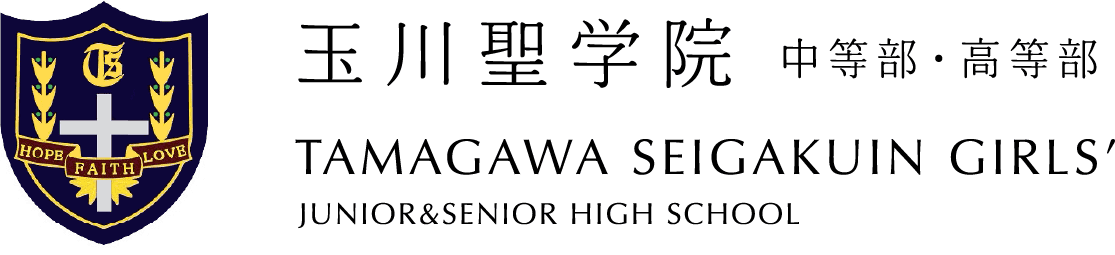今年東京では気温25度以上の夏日が141日、真夏日(30度以上)が90日続いたと報じられた。そして秋の風情を楽しむことが少なく、冬が突然やってくる気候に見舞われた。春と秋という、人間の五感で味わい楽しみ、愛でる季節が失われてしまったような残念さを強く感じた年だった。それは気候だけでなく、あらゆるものがまるで2つのうちの1つという幅しかない、白か黒かしか認めない二者択一の中に答えを求める社会を象徴している様相にも思えるのだ。
人と人とのコミュニケーションが断絶していることを本当に残念に思う。身近な人間関係から政治問題にいたるまで、他者を味方と敵に分けて考える。それ以外の人には無関心であり、その存在は単なる風景にすぎない。だが自分との関わりが生じると、こちら側の人か向こう側の人かを吟味し人を判断する。そんな空気が満ちている。絶対的に欠けているのは対話であり、対話を生み出す人間としての共感力だろう。
本来、人間は生まれたときからこの共感力を備えており、一方的に愛され、助けられる親子関係の中でそれが育まれていく。守られ愛された体験から、愛する心、人を思いやる心が紡ぎ出されていく。言葉はその生身の人間関係を育む重要な架け橋となる手段であった。人は人との関係の中で人間になっていくとは、人との相互関係の中で言葉が開かれていく時に培われていったといってもよいのだろう。
最近出版された人類学者の山極壽一氏の「共感革命」(河出新書)の中で著者は、長い間「共感」により他者と共に暮らしてきた人間が、仲間以外は憎み合い争い合う存在となってしまった現実を紹介し、本来の共感の必要性を論じている。
「人間は赤ちゃんや幼児の頃から共感力を持っている。だが、認知能力が低いために自分と
相手の差が分からない。成長するにしたがって認知能力がつき、相手を助けようとしたり、みんなで協力して困っている人を助けようとする気持ちが湧いてくる。だから私たちは
成長の過程で、様々な体験や学習を積まなければいけない。コンパッションまでを含む共感力は、経験し学習することによって向上できるのだ。」
共感(エンパシー)は認知能力を高めることで、誰かを助けたいと思う同情(シンパシー)を生み、さらにみんなで助けようという思いやり(コンパッション)を生んでいく。それが人間の成長だと説いている。
コミュニケーションの断絶は、人を分断させ、二項対立を生み、人を孤立させる。私たちの社会が失ってしまったものは、意見の違いを超えた「対話力」だといわれるが、そのための前提となるのは、人間としての「共感力」ではないだろうか。著者が言うように「共感力を高めるためには一つの場で、みんなで学ぶことが必要だ。そこで心や体を同調させたり共鳴させたりする体験が重要」なのだろう。学校とはそういう場所ではないか。画面越しの文字中心の教育では育たないこの力を養うことが、簡単に答えの出ない問題に対し、異なった意見を持つ人たちと一緒に、納得できる解を求めて行く力を養うことを促していくだろう。白と黒の間に広がる灰色の空間の中に、何かを見つける感性と知性を大事に育てていきたい。