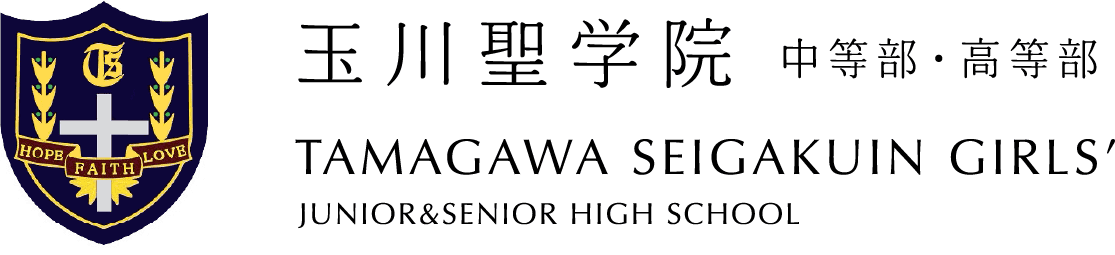東日本大震災から12年が経過した。震災直後に小学校に入学した子どもたちが高等学校を卒業する。震災直後に語られた社会のあり方の根本的な見直しは、どう実現したのだろうか。人間の生き方への再検証を行わず、エネルギー確保のために原発再稼働が急がれている。あの時、これからの方向性を社会全体で立ち止まって考えたのではなかったのか。
新聞の書評欄に惹かれて、モリス・バーマン著『神経症的な美しさ〜アウトサイダーが見た日本』(慶應義塾大学出版会)を読んだ。本文だけで300ページを超す著作で、日本文化の特徴とその現在地について語っている。社会に起きている現象や出来事を明快に分析しているので興味深く一読した。西欧の模倣を通して近代化を急いできた日本の精神構造の変遷を、アメリカとの比較を視野に入れつつ書き綴られている。知的好奇心を啓発される興味深い内容だった。
著者が「神経症的」と記すのは、明治以降と戦後の二つの時期に、日本人の多くが西欧モデルへの憧れと伝統的な考え方の狭間で着地点のない心の揺れを経験し、早すぎる変化がもたらした心の分裂の後遺症が、まさに神経症レベルであると見ていることによる。心の空洞を埋めることができない現実が映し出されていた。
何もかもリセットし新しい時代に適応しようとするあり方は自己を否定することにつながるが、それができるのは自らの哲学や倫理が空疎なものであるからだろうか。著者は日本に起きている魂の喪失が生み出す現象を、精神の空洞化の延長線上に捉えている。明治期と戦後に人々が拠り所としたのは、アメリカンドリームでもある物質中心主義の成果を獲得することであったゆえ、資本主義が煮詰まってしまった現代、脱出の道を見出せないのだ。
東日本大震災によりその拠り所の危うさを思い知らされたはずだが著者は「自由放任主義の成長モデルに固執しようとするが故に、ゼロ成長経済への転換や、よりシンプルな生活様式への転換が通常のビジネスに代わる自明の選択肢として現れるまでにあと何回フクシマが起らなければならないのだろうか」と語っている。それはモデルとなっているアメリカへの批判でもあった。
自己を持つことは容易いことではない。特に同質性の強い私たちの社会では難しさが横たわっている。先日、強烈な自我を表現した19世紀末ウィーンの画家エゴン・シーレの絵画を上野で鑑賞した。究極の自己を描いた「自画像」の前にしばし佇んだ。次第に訴えかける何かを感じていた。毀誉褒貶の中で、スペイン風邪のために早逝した芸術家は「戦争が終わったのだから僕は行かねばならない。僕の絵は世界中の美術館に展示されるだろう」と未来を見据えていた。
個人が個として生きようとする時、そこには軋轢が起きる。集団の中に埋没している方が楽なのかもしれない。だが真実なあり方を貫こうとした時に初めて、人は本来の自分を生きることができるのだろう。人格はその時に完成に向かって動き始める。
人は人生の歩みの中で、突然の出来事により立ち止まらされることがある。その時こそ自分を顧みて、自分の有り様を見直す時なのだろう。その機会を逃さないことが心の空洞化を防ぐ唯一の方法ではないか。自分の現実を俯瞰するとともに、もう一つの別の視点から自分を振り返ることが求められる。真実な宗教が提供する生き方は、その時に意味を持ってくるのだろう。卒業していく生徒たちが、主体的に自分の人生を歩んでいくことができるようにと祈りたい。