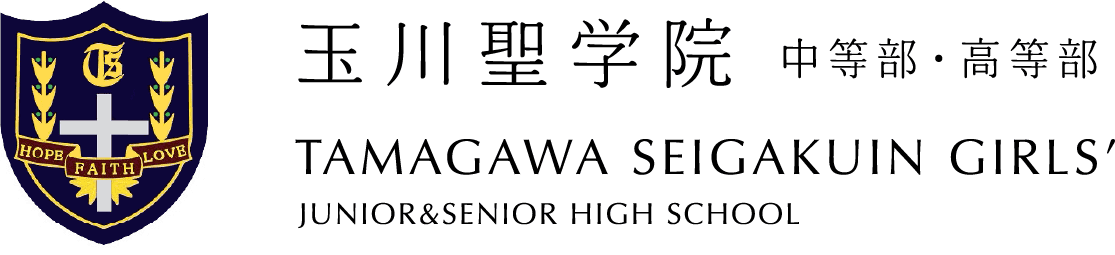新型コロナウィルスの蔓延が子供たちの育ちに影響を与え始めて、すでに2年の歳月が経過した。この3月に卒業を迎えた生徒たちにとっての学校生活は、大きな制限の中の年月であったことをあらためて思い返す。生徒たちの成長を支援してきた教職員にとっても、生徒たちの具体的な学校生活を不足ないものにするための試行錯誤の連続であった。その努力もあり生徒たちは、心に深く刻まれた特別な日々を経験できたのではないかと思っている。
暗中模索はまだしばらく続きそうだが、困難の中で見えてきたこと、大事にしなければならないと気づけたこと(それは教育の本質に関わることである)を、これからの歩みの中で生かせたら幸いだ。歴史や伝統は本来、過去の経験や事実の上に積み上げられていくのだが、残念なことに人は同じ誤りを繰り返す。今、ウクライナで起きている現実の出来事は、映像で見てきた20世紀の悪夢の再現のようにも思える。生命の危機に晒されている人たちに何の支援もできない我が身の無力さを感じ、世界が取り込まれていく恐怖の連鎖に思いを巡らす。同時にまたしても攻撃的な言説や安全地帯からの無責任な発言が垂れ流されている我が国のメディアのあり方と、それに反応しているネット社会の有り様に心塞がれる思いが募る。
3月の読書会もオンラインで行ったが、熱心に学ぶ方々と共に、北海道浦河の「ひがし町診療所」で起こっている事柄を紹介した、斉藤道雄著「治したくない」みすず書房 を取り上げた。何年か前に同氏の著書「悩む力」(みすず書房)を一緒に読んだ。精神障害者が共に働くコミュニティ「べてるの家」で実践されている生き方について学んだ。今回はその続きとして、精神科病棟から退院し、町で暮らすようになった精神障害を抱えた人たちの生活ぶりを中心に、開業した川村敏明医師と診療所スタッフたちの、精神障害者たちとの関わりの記録が紹介されていた。
日本には世界中の精神科入院患者用ベッドの5分の1が存在すると言われている。諸外国では例を見ないほど長期入院者が多く、病院が収容施設化している。確かに統合失調症の治療法は確立していないので症状を緩和するだけが医療の現実だが、患者を社会から隔離して見えなくしているように思えてならない。同質社会では異質な者は排除されがちだ。しかしこの浦河では、患者たちが悩みながらも地域で生活することを、医療関係者のみならず地域全体で支えようとしている。悩みながらも当事者たちは自分を開き、周囲は排除するのではなく一緒に悩もうとしている。すると幻聴や妄想を抱えながらも、当事者たちは市井で生活できるようになる。失敗もあるが生きる喜びや共にある幸いを体験するようになっていく。人間性を信じて開放医療を進めている取り組みが、感動的に紹介されていた。
読んでいるうちに、これは精神障害の問題だけではなく、主体性が求められる教育の方向性も、断絶が広がる社会が目指すべき共生のあり方も、そして答えの出ない事態に向き合っている世界の現実に対しても、同じ原則が適応できると思わされた。自分の主体性をどこに置くかにかかっていることが示唆されている。浦河の人たちが長い間悩みの中から見つけ出そうとしているものを、自分のフィールドで同じように悩み続けていく中で見つけ出したものだけが「本当のもの」なのだろう。目の前の現実にしっかりと向き合っていくことを続けるしかないと思わされた。時宜に叶った学びの場だった。