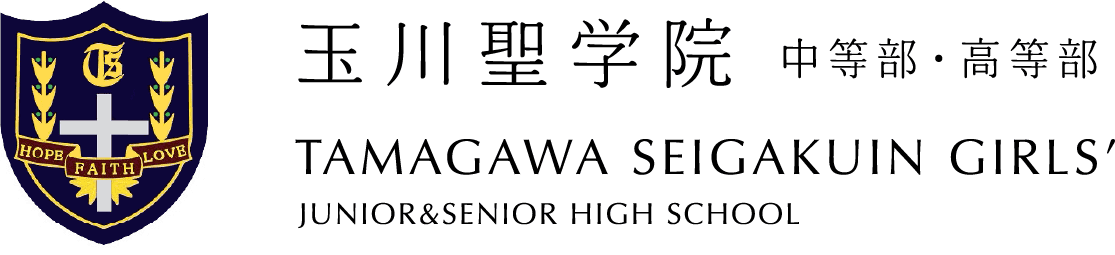2月の読書会ではノンフィクションライターの杉山春氏の「児童虐待から考える」(朝日新書)を読む。父母からの虐待で命を落とした子どもたちの事例が記されている。その当時には大きな話題となり、加害者である親に非難が集中した事件も、気がつくと別の事件に関心が移っていて、そんな事件もあったなと、記憶の底からすくい上げるような気持ちで記録を読み進めた。著者は加害者の生い立ちや事件の背景を丹念に追い、背後にある加害者の抱えた社会的な問題に光を当てる内容になっていて、考えさせられることの多い本だった。
暴力は連鎖する。幼い時の負の体験は時に同じ過ちを繰り返すことになる。必ずしもすべてがそうなるのではなく環境要因が大きい。そして一旦「枠」が崩壊すると、あっという間に奈落の底に落ちていく危うさを抱えつつ、多くの人が生きていることに考えさせられた。愛される子と愛する親という基本的な愛着の関係が逆転してしまう問題性が、親自身の原体験の乏しさゆえに表面化してしまう恐ろしさを感じた。自信がなく自己肯定感の低い親ほど、子どもに強圧的になっていくというメカニズムは、この社会全般にわたって蔓延っている傾向なのではないかと思う。
本来、親子であろうと人間として対等であるという考え方が、国連子どもの権利条約で掲げられてから30年が経過した。子どもの権利を子ども自体の人権問題として向き合おうという方向性が採択され、世界はその実現に向かって動き始めている。日本の厚労省も「虐待」への対応として、子どもの人権への配慮の立場から、家族から分離して社会全体のセイフティネットづくりの方向性が提案されている。
しかし同じ政府が、改正教育基本法に基づく家庭教育支援法案の成立を目指しており、そこには「子育ては親の義務と責任」であると記し、子どもの権利について触れられていない。対等性は全く眼中にない原案となっている。教育と養育のあり方が問われている。
対話(dialogue)とは、両者が互いの中にある真理を分かち合う中に生じる発見を目指す行為だが、その前提は両者が対等であるということだ。立場は異なっても人間としての対等性が確保されないところに対話は成立しない。いかに教育という世界に対話が乏しいか。対話を知らず、身につけずに社会に出ていく人たちが多いことか思わされる。未だに支配=服従関係を強要されることが実に多いのではないか(パワハラ、セクハラはその典型)と考えさせられた。
この対等性は、個人が尊重される社会においてのみ成立する理念だ。個人が集団の中に埋没し、集団への同化を強制される社会で対話は生まれにくい。ネット上に飛び交う攻撃的で扇情的な言葉の多くは独りよがりの戯言だが、歯車が合わずに自己の意識の肥大化だけを生んでいる。しかしそういう集団への同化を誘う動きの中から、全体主義は生まれていく。
2020年になり一斉に放映し「みんなで・みんなで」と何回も繰り返したオリンピックへの啓発を狙うテレビ局合同のCMに、自分としてはひどい違和感を感じた。反対することができなくなるような空気が醸成されることへの危惧なのかもしれない。「主体的・対話的な深い学び」という新しい学習指導要領の方向性を、単なるお題目にしてはならないと心から思う。目の前の生徒・学生、同僚、保護者を対等な存在としてリスペクトするところから本当の教育は始まるのであろう。