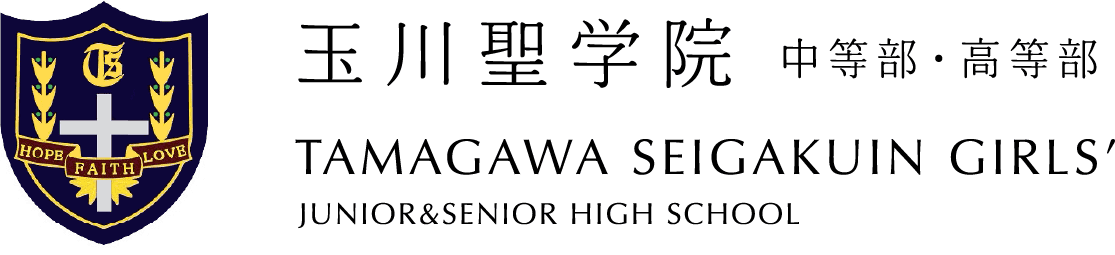今月のPTA読書会では工藤直子さんの詩(日本語を味わう名詩入門「工藤直子」萩原昌好編 あすなろ書房)を読んだ。25編の詩が取り上げられ、それぞれに萩原さんの文章が付けられている。参加者には予め、「今日、心の響いた一編を 後で分かち合いましょう」と言って、読み始めた。
工藤直子さんの詩は、あの「のはらうた」に象徴されるように、動物や植物、眼に映る自然までもが、それぞれの人格を持っていて、対等な関係の中で対話をしているように思える独自の世界が展開されている。宇宙もミジンコも一つの名前を持っていて、互いに出会うことができる。風も麦畑も欅の木も小鳥も対話している。工藤さんの心の奥底に潜む「原風景」がそれを可能にしているのだろう。遠い昔の記憶の底に、原風景を持てることは幸いだ。今の子ども達の心の奥にはどんな風景があるのだろう。
25編の一編一編を読んでいくと、何か嬉しい気持ちになったり、広い気持ちに満たされたり、深い頷きが与えられたりしたのだが、その中で今回いちばん私の心に響いたのは、「ばら」というタイトルの短い詩だった。
「花びらが散ると そこに 花びらのかたちの
なにか やさしいものが あつまるように思われる」
ばらの花が散った後、不思議なことになお一層花が鮮やかに咲いているような印象を受けると歌われている。生と死が連続線上に描かれているところに工藤さんの詩のもう一つの特徴があるが、ちょうどその週のニュースで、アフガニスタンで長い間活動していた中村哲さんの訃報が届けられたことで、今回、この詩が深く心の届いたのだ。
中村哲氏の著書も何年か前の読書会で取り上げたこともあったが、私は何回か直接お話を聞く機会があった。そこに必要があるからそれに応えていくと語る姿は、率直な人間味あふれる魅力に満ちていた。その彼が襲撃されて亡くなったという事実は、本当に心を苦しめる出来事だった。あんなに現地の人たちの必要に応じて、苦労を重ねながら彼らの生活の再建に惜しみない努力を続けてきた人が、何故このようになってしまうのか、やり場のない怒りと悲しみが心を覆った。この後に起こりくる絶望的な事態にも恐れを感じた。
そんな中でこの詩を読んでいるうちに、別な何かが心に届いたことを感じた。中村さんの死後、まさにアフガニスタンに起きていた事実を見、中村さんたちの真実に眼を留めてその働きを継承しようとする誰かが現れるだろうということに思いを馳せた。亡くなった事実ではなく、そこにある「花びらのかたちのなにかやさしいもの」に眼を留めて、その優しさを受け継ぐ誰かが登場することを思うことができた。
かつて玉川聖学院の生徒たちは、中東でIS殺害された後藤健二さんの死の知らせを聞き、深い悲しみを感じたが、その後、託された使命の実現に向けて歩み出すことを決意して、多くの生徒たちが誰かの役に立ちたいと思い進路選択をしていったことを思い出した。
中村さんの死を「二人称の死」と受け止めて、それを心に刻む人たちが数多くいることを確信し、そのことが確かなリアリティを持って心に迫ってきた。「やさしいものが集まるように思われる」そのような社会でありたいと心から思った。そんなことを、私は分かち合いの場で、集まった方々と分かち合うことができ、慰められる午後となった。