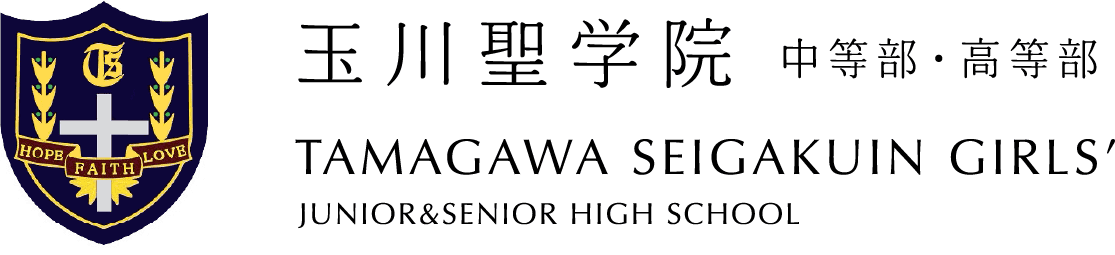新聞の書評を見て興味を持ち一冊の本を読んだ。強制収容所体験を書いた「夜」の作家ヴィーゼルの薫陶を受けたアリエル・バーガーが書いた「エリ・ヴィーゼルの教室から」という本だ。ノーベル平和賞を受賞したヴィーゼルは、作家であり差別や圧政に対して行動するジャーナリストであると思っていたが、ボストン大学教授として真理を求める学生たちとの対話を重ねる授業を展開していた教育者であることを知った。その授業内容は大変刺激的で、非常に啓発されるところの多い内容であった。
ヴィーゼルはハンガリー生まれで、幼い頃にユダヤ人としてアウシュヴィッツ強制収容所での生活を余儀なくされた。家族を失い大きな喪失感を抱えて戦後フランスの孤児院で育った。やがてユダヤ教の指導者となったが、戦後世界各地で起こり続ける現実の世界の不条理と向き合いつつ、文学や哲学を論じ続けてきた。この本は彼が大学で行った講義を、弟子であった著者が尊敬と感動をもって読者に伝えてくれたヴィーゼルの遺言のような作品だ。久しぶりに知的好奇心を掻き立てられる内容だった。
議論は神学から哲学、人間の狂気や疑い、究極の人間性や心の奥底に深く残る傷や痛み、他者との関わりや憎しみ、神の沈黙への問いかけなど、多岐に渡っていたが、どのページからも自分の生を全うするために苦闘している一人の人間の真実が伝わってきた。こういう講義に触れることができた学生はなんという幸いだろう。問うことで問われ、疑問を投げかけることで自分の内なる闇と向き合い、批判的な思考の中から真実への道を探求し、断絶の向こう側に微かな連帯への希望を見出していく。それを引き出していく教師としてのヴィーゼルの真実性が際立って伝わって来る。圧倒されたという想いというよりも、真実を求めるということのモデルに出会っているような感じを持ちながら、読み進めていくことができた。
先日、30年ほど前にカウンセリングを共に学んだ旧友と分かち合う時をもった。実習生の頃、演習の中でトレーナーが悲しそうに「今、クライエントの心が死んでしまいましたね」と宣言して、私たちの未熟さを指摘してくれたことなどを思い出した。一生懸命に取り組んでいたはずなのに、辛辣なコメントを幾度ももらい、いたたまれなくなり帰りたくなった合宿の経験を語り合った。同時にひたむきに何かを求めていた時代を懐かしく回顧した。あのような経験がどれだけ貴重な体験であったかを改めて思い返した。
今、自分は何をどのように求めているのだろう。現場を離れて「教えること」に専念してしまっている自分の現実を振り返る。多くの学生と接しているようでいて、目の前の人間の痛みや悲しみが見えなくなっているのではないか。対話を通して引き出されていく真実を、今の自分は体験しているだろうか、持っているだろうか。教育とは「人から人にしか伝わらない」真理を伝えていくことだと思うが、それは絶えざる自己研鑽と自己開示の営みの中からしか紡ぎ出されない。自分の内なる心を映し出している鏡を、磨き直さねばならないと改めて思わされる。
ヴィーゼルの言葉が重く響く。「他者の、自分とは違う点がわたしを魅了する。」「何を学ぶ時でも、これだけは忘れないように。学習によってあなたがたはより人間的にならなければならない。その逆ではありません。」