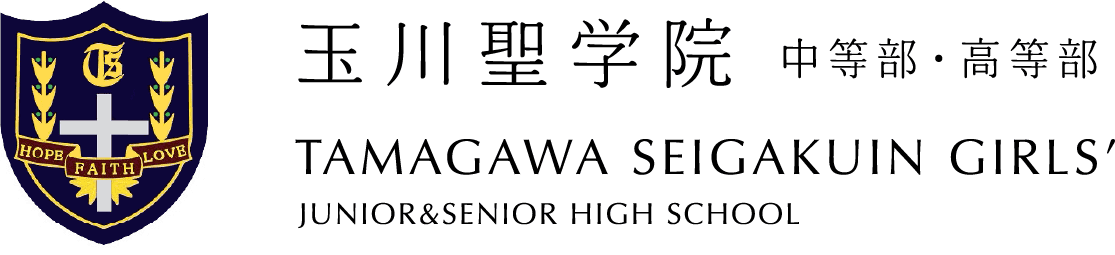先週9月の「保護者のための人間学読書会」で、上橋菜穂子さんと斎藤慶輔対談さんの対談集「命の意味命のしるし」(講談社)を読んだ。ファンタージー作家と野生生物を守る獣医師との対談は、大変興味ふかい内容だった。その中に出てくる一文に、深く考えさせられた。
斎藤慶輔さんは人間社会との接触による事故で傷ついた、釧路湿原のオオワシなどの猛禽類を手当てして自然に戻す働きをしているのだが、このように書いていた。
「私は、猛禽類を専門に診ていますが、もし目の前に弱った動物がいたら、ワシやタカはどう思うのか。おそらく「しめた。コイツは襲って、食べられるぞ」と思うに違いありません。「おいしそう」と思うことはあっても「かわいそう」とは思わないでしょう。まして「直そう」だなんて思いもしない。そんなことを思うのは、おそらく人間だけです。なぜ、人間だけが、傷ついた他者を治そうとするのか。あらためて考えてみると、なるほど、不思議な話です。」
人間は傷ついた他者を治そうとできる、他者の痛みや苦しみを想像することができると言う発見は、人間の特性を物語っているように思う。人は様々な他者との関係性の中で知恵や知識を身につけ、自分の考えを形作っていく。20年という長い年月をかけて大人としての自我を身につけていく。他者の助けを得なければ生きられない未熟な状態として生まれ、養育者(親)との関係性の中から、愛されている自分を確信し、愛されるに値する自分の存在を認識する。その時初めて、他者への積極的な関わり(愛)が自分の内側に芽生えていく。こんな人間の営みが、他者を助けようとする思いを生み出していくのではないか。また、生物学的には大変弱く、何も攻撃的な武器を所有していない人間は、集団を形成することで外敵からの攻撃を防ぎ、集団の一員を守りあうことを通して社会的な絆を深めてきたのではないか。
果たして現代社会は、本来持っている人間の特性を生かしているだろうか。群れから彷徨い出た羊が捜し出されることを喜びとしているか。「自己責任」として排除されていないか。いや他者の失敗は非難と攻撃の対象になってしまっていないか。社会全体が弱さを包み込む包容力を失ってしまっていないか。そうだとしたら、人間は人間であることを忘れてしまうのではないか。
昨今のメディア報道の方向性は、多くの人が好奇心を持ち、知りたいと思う事件や出来事を徹底的に追いかけているように見える。そこにあるのは販売部数や広告企業が求める視聴率の数字への応答であり、真実やメディアをしての使命とは別の力が働いているように思う。人の好奇心をくすぐり、対象事件の「賞味期限」があるうちはそれを徹底的に利用し、傍観者として攻撃的な主張を繰り返す。ネット上では一般人のさらに攻撃的な言葉が並んでいる。そんな光景を見せつけられる。
人間の特性は、弱さを包み込む力、すなわち愛が心に宿っていることにあるのではないか。幼い頃の原体験として、愛されたという記憶が心の奥底に刻まれることによって、愛する行為が自然に備えられていく。そういう人間の営みが文化を育んできたことを、しっかりと伝えていくことが教育の役割ではないかと思わされている。