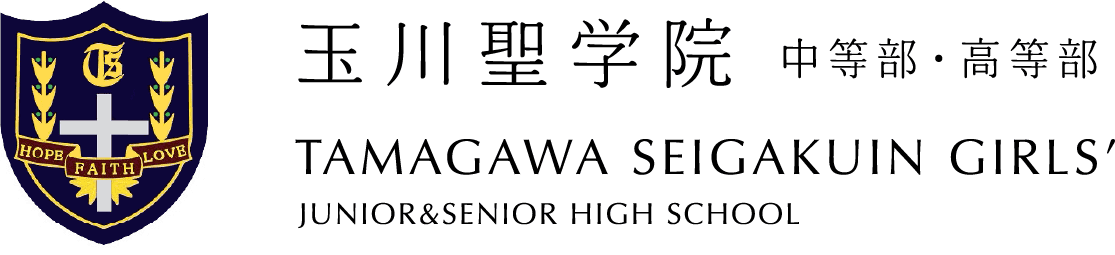私たちはトランプ大統領に象徴されるような「自己主張」が力を持つ時代の中に置かれている。政治がパワーゲームのように弄ばれ、社会と世界が分断されているように思えてならない。日本の国会の議論も全く噛み合っていないことを見せつけられている。人格的交流の道具であった「ことば」の持っていた権威は失われ、記号化された言葉は攻撃的な主張や公然とした嘘の情報の発信、差別や憎悪に満ちた感情の流布のために用いられ、人と人を繋ぐ貴重なコミュニケーションの手段ではなくなってしまったように思えてならない。言葉を通して知識や価値を伝えようとする教育に、何ができるのだろうか。
暉峻淑子氏が「対話する社会へ」(岩波新書)の中で「対話のない社会はいつか病み、犠牲者を出し、平和はある時、あっけなく崩れてしまうのだということを全身で感じるようになりました。」と指摘しているように、平和を支えるには社会の中に対話的態度を根付かせることが必要なのだろう。文科省は改訂される新しい「学習指導要領」の中で、「主体的対話的な深い学び」こそが重要であると繰り返し書き記しているが、そもそも正解や模範解答のない今日の社会問題に対して、思考停止状態に陥らずに、より主体的で建設的な選択をするためには、他者を信じて「互いに持ち合う真理を分かち合う対話」(dia-logos)は、どうしても必要なことなのだろう。やはり「ことば」の力を信じることからしか、教育は始まらないのではないかと思う。
勧められて、評判になっている映画「主戦場」を渋谷の映画館で観てきた。見解が二分している「従軍慰安婦問題」に対する各界各人の証言や主張を撮り重ねたドキュメンタリー映画だ。登場人物同士が議論しているわけではないが、対立する意見を並べることで、見ている者に判断を委ねようという制作者の意図は伝わってくる。映像は語り手の心模様を雄弁に語ってくれる。見ている私たちは、言葉とともに登場人物の表情や仕草の中に、語り手の人格を垣間見ていく。記号化された言葉の奥にある一人一人の人格が容赦なく映し出されていく。事実とは何か、真実はどこにあるのか、歴史認識はどのように作られていくのか、そして私はどこにいるのかを問われていく不思議な映画だった。同時に、昨今のメディアに登場するコメンテーターと言われる人たちの「言葉の軽さ」「無責任さ」を思い知らされた。そしてどの分野においても、地道な研究を継続している「専門家」が本当に必要であることを実感した。
言葉は議論するため、勝ち負け、善悪、優劣を競うための道具ではないだろう。対話を成立させる条件は、たとえ目の前の相手と意見が違っても、相手を人間としてリスペクトできるか否かにかかっているように思う。人格を否定し、文化や思想を見下し、自己の正当性のみを主張することの中には、真の対話は生まれない。教育の現場でそれをどのように実現できるか、真に平和を求める社会を構築するために、この力を養成することが今日の学校教育に課せられた喫緊の課題であるように思う。