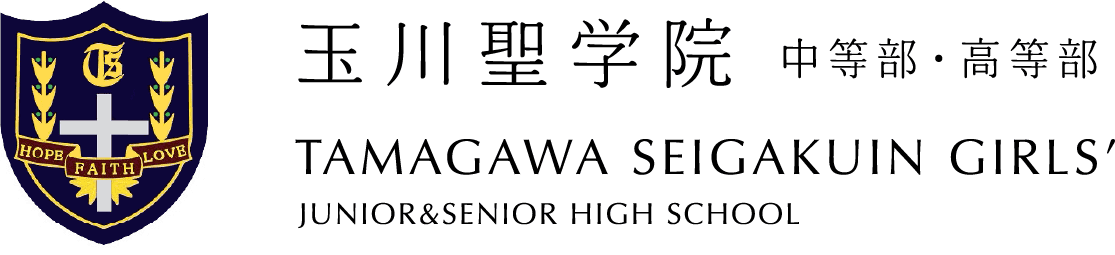絵本作家・いわさきちひろの評伝「いわさきちひろ~子どもへの愛に生きて」(長男の松本猛著 講談社)を読み、ちひろ美術館に行きたくなり、先日練馬区下石神井にある、ちひろ美術館・東京に行ってきた。折しも、「日本の絵本100年の歩み」の展示と、この美術館開館40周年の記念展示が並行して行われていた。子供連れの若い親子が訪れていたのが印象的だった。おそらく母親も小さい頃にこの美術館を訪れた経験があるのだろう。子供たちに絵本を開いている母親たちの顔の中に、穏やかで平和な空気が満ちていた。
日本の絵本の歴史を見ながら、いろいろなことを考えていた。特に大正デモクラシーと呼ばれる空気の中で、一斉に花が開くように童話・童謡・童画の運動が盛んになり、質の高い絵本や雑誌が作られていく。デューイやフローベル、モンテッソーリなどの「新しい教育」が流入し、子供の発達を中心に置いた教育理論の基づく私立学校が生まれていった時代の色や匂いを、子供の本の中に感じることができた。戦争が近づく昭和になると、色彩がガラッと変わっていくのも実感できた。芸術は時代を映す鏡だと言われるが、もしかすると子供たちの文化の中に、それは最も象徴的に現れるのかもしれないと思った。
もう一つ気づいたのは、いわさきちひろさんの受けた教育に関してであった。のちに彼女自身が回顧しているように、青年時代を戦争によって奪われてしまった世代であったにもかかわらず、戦後に独特の絵画芸術を花開かせていったのは、女学校時代の教育(府立第六高等女学校)の教育にあったのではないかということだった。この学校に入学してきたのは選ばれた女子生徒たちではあったが、校長の丸山丈作氏の自由な教育は成績をつけずに、芸術や体育などの実技教科を重視し、旅行的な行事に力を入れるユニークな教育であり、戦争に近づく時代の中にあって画期的な教育を推進していた。暮しの手帖の大橋鎮子氏やシャンソン歌手の石井好子氏など、戦後文化に貢献した卒業生たちを輩出しているのは、この女学校の教育の賜物ではないかと考えた。
思春期の魂の奥底に植え付けられた、美しいもののイメージ、素敵な体験や自尊感情は、その後の困難な時代を通り越えて、花開く季節を迎えていく。それは決して有名になることではなく、独自の視点を持った自分の人生を切り開いていくことにつながっていく。いわさきちひろさんの絵画の色褪せない魅力とともに、時代を超えて伝わるものの確かさを考えさせられた。教育の影響は大きい。「道徳が教科化」されるこれからの時代、私たちは何を子供たちに伝えていけるのか、いよいよ教育の質が問われる時代に突入していることを深く思わされた午後のひとときだった。