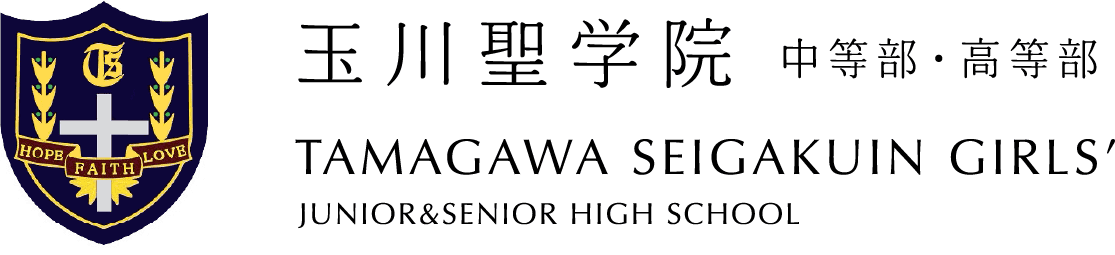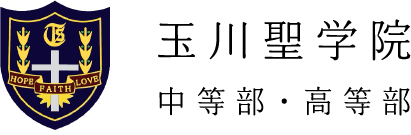聴覚に障がいを持つ子たちの学校(ライシャワー学園)の教育と関わるようになって深く考えさせられてきたのは、言葉の不思議そして対話の重要性だった。言葉は決して教えられるものではなく、自らの内側からの反応として生まれてくるものであり、人と人との対話を通して、言葉の世界は広がっていくということだった。言葉を通して人は世界を豊かにしていくことを体験的に知らされている。
人と人とが分断されている現代、言葉は自らの感情を表現する単なる記号のように表出され、時として他者を攻撃し排除する道具として用いられている。そこには用いられている互いの言葉が示す世界の違いを確認して、相互理解を深めようという対話の精神は働いていない。仲間内にだけ「イイね!」と言われる言辞を弄して、言いっぱなしの状況が溢れかえっている。言葉の世界が痩せ細っているように思えてならない。
今月の読書会では、長田弘さんの『読書からはじまる』(ちくま文庫)を共に読んだ。詩人の言葉はキラッと輝いている。記されている文章の各所から啓発された。なかでも言葉に関する考察は、自分が思い描いている現実を、わかりやすく表現してくれた。
「言葉の豊かさとは、どういう自分であるか、お互いにどういうふうに違っているかを進んで語ることができる、そういう豊かさにほかなりません。・・・・言葉というのは、人の生き方の流儀であり、マナーです。言葉を豊かにするというのは、自分の言葉をちゃんと持つことができるようになることです。流行の言葉や借用の言葉に、決して自分を預けてしまわないことです。言葉は赤ん坊が言葉を覚えてゆく時のように、ただただ学ぶのでなければ手に入らないのです。」
著者は「人間が言葉をつくるのではありません。言葉のなかに生まれて、言葉のなかに育っていくのが人間です。」と述べ上記のように語っている。そして言葉を学ぶとは勉強することではなく、自分に必要な言葉をどう使って話しているのかに気づいていくことだと述べている。その上で、本を友達にすることを通して、自分を更新していくことを勧めていた。
人と対話することは、相手の人格を認め、対話(ダイアログ=「真理は二人の間にある」)を通して、より豊かな世界を発見していく営みなのだろう。そもそも教育の場とは、そういう真理の伝達の機会であったのだろう。そして今日の教育に求められている「主体的・対話的で深い学び」とは、知識を教え込む授業から、新しい言葉の意味を発見するために、子ども達自らが試行錯誤しながら、語り合っていく授業への転換が図られることであるのだろう。社会全体がそれから遠く離れた所にある現実の中で、どうそういう気づきを提供できるのか、現場の教育力が試されているように思われる。