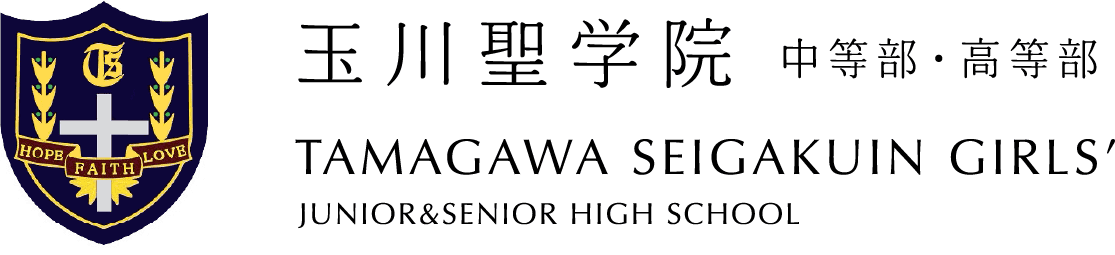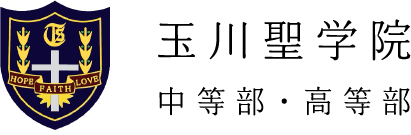保護者や卒業生保護者と一緒に読書会を始めて16年目になる。年間10冊として150冊の本を一緒に読んできた。その準備をする度に、著者の社会や人間に対する思いをわかろうと、想像力を働かせることは楽しいことだった。それは多くの場合、今まで持っていた既存の知識を新しいイメージを作り変える作業を伴っていた。情報を得るというより、心の世界を広げてくれる経験であったように思う。選書が自分の読書志向に偏る傾向があったが、それでも意識的に今まで縁遠い分野の書物を選ぶことで、視点が広がり豊かな発想を持つことができたように思う。一人で読んでいたらそうならなかっただろう。少なくとも本の概要を説明し整理して提示する役割を与えられた故に、少々苦痛でも丁寧に書物と向き合えた年月だった。機会を提供してくれた方々に感謝したい。
この度フランクルの『それでも人生にイエスと言う』(春秋社)を取り上げ、読み直した。戦後間もなく、ナチスの強制収容所から解放されたフランクルが、ウィーンで行った連続講演の記録をまとめた書物だ。「人間学」の授業の中で生徒たちの行う読書紹介でも毎年取り上げ、発表されている名著だ。保護者読書会でも十数年前に一度取り上げたことがあった。
記されている内容は、フランクルの『夜と霧』でも紹介されているように、アウシュビッツという極限状況を体験した精神科医が洞察した人間の脆さと尊厳について語られている。何度も読み返し、思想の全体像はわかっているつもりだった。
だが読み手の状況が変化すると、見えてくる世界が違うことに気づいた。その新鮮さに驚く。取り上げられている事例、著者が見てきた人間たちを通して気づけた確信が、今までとは異なった説得力を持って自分に迫ってきた。自分が歳を重ねてきたからだろうか。多様な人間模様を自ら体験してきたからか、それとも余計なものが剥げ落ちたから見えてきたのだろうか。何れにしても自分自身の心の状態で、こんなにも見えるものが違うことに気付かされた。
「ニヒリズムを克服するためには、人間として生きている意味と価値を絶対的に信じなければならない」と語る著者の心は、大衆に向かうのではなく一人ひとりに呼び掛けられている。「人生が一人ひとりに出す問いに、具体的な行動を持って答える」ことを通して培われる人間力が、その人を「本当に自分」にしていくのだろう。読み手の持つ世界観は、このような書物と出会うことで変容の契機が与えられ、変容することでさらに見えてくる世界があり発見がある。その繰り返しが読書の愉しみなのではないか。
書斎に高く積み置かれている書籍のうち、どれだけの本が再読されることを待っているのだろうか。読み飛ばした本の中に、今ならわかるメッセージが隠されているかもしれない。そう思うと知の宝庫の前に佇んでいることを嬉しく思う。きっとこれで部屋の整理ができないだろうなと思いつつ、少し余裕が持てたら読み直してみたい本をリストアップしている自分がいた。