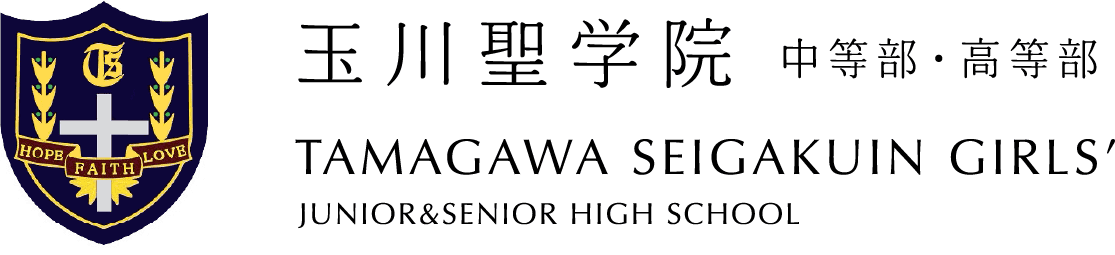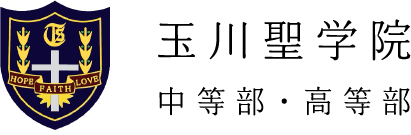今年は戦後80年の節目に当たる年だが、広島・長崎の被爆生存者は今年3月時点で10万人を切ったことを厚労省は発表した。平均年齢は86歳、証言者の声を直接聞けなくなる日が次第に近づいている。核兵器廃絶を求めるためにも被曝体験の継承が求められているが、我が国の中にも核の悲惨さに想像力を持てない者が、国会議員となる時代になってしまった。
歴史との対話は「垂直のコミュニケーション」だと言われる。そしてこの対話を失った時に、未来は危ういものと化す。現在しか見えなくなるからだ。だが歴史を改竄して都合良く解釈しようとする営みは、自己を正当化し過去に盲目になろうとする人たちの間で、いつの時代にも起きてくる。だからこそ過去に思いを巡らせる時、節目に立ち止まって考える時が必要なのだろう。
この夏は節目の年でもあり「平和について」考える機会が多くあった。ウクライナの戦争は続き、ガザでは信じられぬ光景が伝えられ、ミャンマーでは力による支配が続く中、私たちは過去の歴史から何を学び、今日の社会に何の貢献ができるのだろう。
かつて東西冷戦が深刻化する中に登場したアメリカ大統領ジョン・F・ケネディは、ソ連との危機的な状態を回避して、違いを乗り越えて共存する道を、アメリカン大学の卒業式で語った。
「なぜなら、平和はプロセス(問題を解決する方法)だからです。平和を求めても家庭内や国内がそうであるように、口論や衝突事件はなお存在し続けるでしょう。世界平和の実現のためには、互いに寛容性を持って共存し、紛争を公正で平和的な調停に委ねるだけです。・・・私たちの好意や敵意がどれほど固定的に見えても、時間と出来事の流れは、時として国家間や隣人との関係に驚異的な変化をもたらすでしょう。ですから忍耐強く努力を続けましょう。」(ジョン・F・ケネディ「平和の戦略」演説 1963年)
ここには対立を煽り、仮想敵国を作り、力による支配を声高に叫ぶ政治家と一線を画する主張があり、具体的で現実的な政治決断を語り、人間の叡智と愚かさを指摘しつつ、国内の公民権運動への理解とも繋がる融和への道筋が提示されている。
今年が戦後80年という節目の実感を持てるのは、どれくらいの人たちなのだろう。今しか考えない人たちにとって、過去の歴史は「教科書の中の出来事」なのだろうか。広島や長崎の小学校では、被曝日を登校日として、被曝体験を語りつぐ教育が継続して行われてきた。日本の祝日には「平和を考えるための祝日」は存在しないが、平和への思いをどのように次世代に継承していくかは、社会全体が担うべき課題といえよう。少なくとも、過去に目を瞑ることがないように、また命を繋いで生きることへの想像力を失うことがないために、次世代に手渡さなければならない大事なことがあることを、この夏は強く感じている。