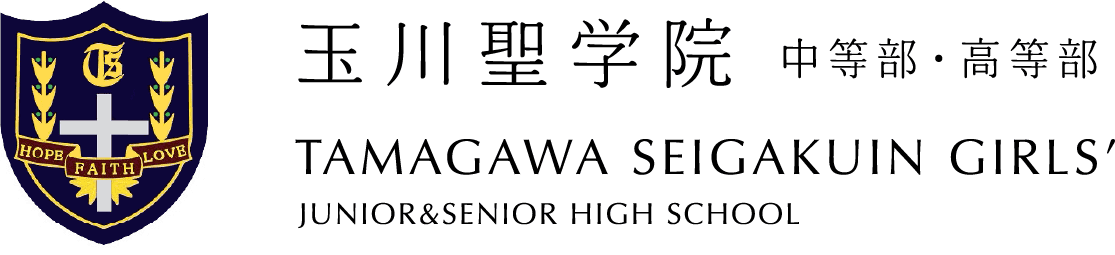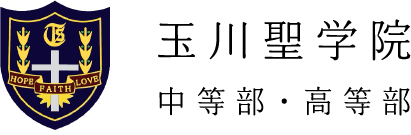参議院選挙が近いからだろう。これからの社会の在り方を声高に主張する言葉が飛び交っていた。近年のネット上には、自分の考え方を訴える短い動画が溢れかえっている。どれも一方的な主張だ。テレビ等の討論番組でも対話の中で問題点を明らかにしたり、互いに接点を見つけようとする努力は全く見られない。言いたいことを支援者に向けてアピールしているだけの様子は、昨年のアメリカ大統領選挙をはじめ全世界的傾向のように思われる。今、民主主義の根幹にある共に暮らす社会を創る思想が、底抜けしているように思えてならない。
最近、レベッカ・ソルニットの本を読んだ。環境や人権問題を取り上げ、ジェンダーの問題を深く掘り下げている作家・批評家だが、支配服従関係を強いる人間関係のあり方の本質が、女性の人格軽視という形で現れていることを書き記している。
「何でもない会話のその先には、男性のみ開かれた空間が広がっている。言葉を発し、話を聞いてもらい、権利を持ち、社会に参加し尊敬を受け、完全で自由な人間として生きられるような空間。そこには女性は入れない。かしこまった言葉で言えばこれが権力が行使される一形態だ。」
(レベッカ・ソルニット「説教したがる男たち」(左右社)
ミソジニーという女性蔑視の観念も根底には、男性優位社会への郷愁のようなものが見え隠れする。だがこの屈折した支配感情は、ジェンダー問題だけではないように思われる。他者を対等な存在と見ない。優劣、強弱、大小、上下で比較し、自分の立ち位置を測る心の奥底に、優越感と劣等感の感情が絶えず渦巻いている。裏返しの嫉妬や妬みも見え隠れする。そんな思いの中で、自分の主張に賛同する人だけに向けての「言葉」が発せられる。
ポール・トゥルニエは、著書『暴力と人間』の中で、関係性の中で優位に立つ者は、人を支配しようとする傾向が強いことを明らかにし、
「力の危険性はずっと恐ろしく深刻なものがあることを指摘したい。それは人と人との真の対話を阻害するということである。今日どこでも対話の必要性が叫ばれているが、対話が行われていることは、きわめて稀である。・・・対話とは、力関係がほぼ等しく相互に対照的な人、あるいはグループでしか実際には可能ではないのである。」 (ポール・トゥルニエ「暴力と人間」ヨルダン社)
と語っていた。対話の必要性が叫ばれる時代ではあるが、その難しさは、人間が本来持っていた相互依存性をないがしろにしてきた歴史が作り出したものといえるもかもしれない。
対話は対等でなければ成立しないということは、各自の人権が尊重され、独自性、個別性が認められる中で成立する営みだろう。異なった感じ方や考え方をする者たちが共に暮らすために必要な人間の知恵が「言葉を交わすことを通して行う対話」だった。
社会の深刻な分断はこの対話の喪失から起こっているのだろう。教育は本来、人間性を育む場所だとしたら、その優先課題は一人一人の尊厳を重んじると共に、「対話力」が身につくような支援を提供することなのではないかと、強く思わされている。